夕暮れ時、研究所の窓からオレンジ色の光が差し込んでいます。
白衣を着た研究者が静かに顕微鏡を覗き込み、慎重に試料を扱います。
その静けさを破るように、世界中へノーベル賞の速報が駆け巡ります。
「ノーベル生理学・医学賞や化学賞を取った」――そのニュースがどれほどの偉業なのか、今回はわかりやすく解説していきます。
Contents
ノーベル賞:日本人受賞の最新状況
まず、直近の動きを確認してみましょう。
2025年、ノーベル生理学・医学賞は、免疫の暴走を抑える「制御性T細胞(Tレグ)」の発見に関わった 坂口志文氏 ら3名に授与されました。
同年、ノーベル化学賞 には、光を使って分子を精密に組み立てる「超分子化学の革新」で世界をリードした 北川進氏(京都大学名誉教授)が選ばれています。
これにより、日本人のノーベル生理学・医学賞および化学賞の受賞者は、それぞれ7人目となりました。
これまでにノーベル生理学・医学賞を受けたのは、利根川進(1987年)/山中伸弥(2012年)/大隅良典(2016年)/本庶佑(2018年)/坂口志文(2025年) など。
また、ノーベル化学賞では、福井謙一(1981年)/白川英樹(2000年)/野依良治(2001年)/下村脩(2008年)/鈴木章・根岸英一(2010年)/吉野彰(2019年)/北川進(2025年)
このように、受賞の間隔は決して短くありません。
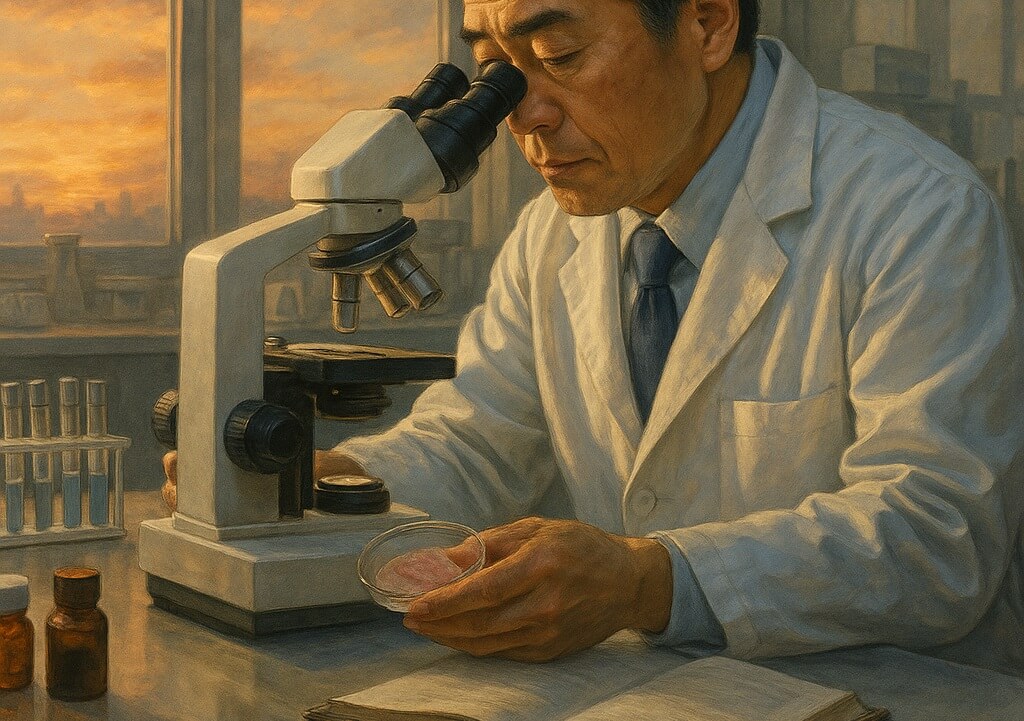
なぜ“凄まじい”と言えるのか
世界的な競争を勝ち抜く難しさ
ノーベル賞は世界中の優れた研究者が対象です。
アメリカ、ヨーロッパ、中国など、多額の研究投資と優秀な人材が集まる国々との競争の中で、日本の研究が選ばれることには確固とした意味があります。
長期間にわたる挑戦
ノーベル賞に結びつく研究は、10年から20年、場合によってはそれ以上の年月をかけて積み上げられます。
アイデアの検証、実験の失敗、資金の確保、再現性の確認など、地道で根気のいる作業の連続です。
短期的な結果が求められる現代において、これほど長く探究を続ける精神力は特筆すべきものです。
国内の環境を超えて成果を上げる
日本では基礎研究の予算や若手研究者の待遇など、必ずしも恵まれた環境とは言えません。
そうした制約の中でも成果を出している点は、個人の努力だけでなく、研究文化そのものの底力を示しています。
数字で見ても希少な成果
日本人のノーベル賞受賞者は、全分野合わせても30人前後、その中で生理学・医学賞や化学賞の受賞者は一握りしかいません。
つまり、確率的にも非常に狭き門なのです。
データで見るこれまでの日本人受賞例
| 受賞者 | 年 | 分野 | 主な業績・意義 |
|---|---|---|---|
| 利根川進 | 1987年 | 生理学・医学 | 抗体多様性の遺伝的原理を解明 |
| 山中伸弥 | 2012年 | 生理学・医学 | iPS細胞技術の確立 |
| 大隅良典 | 2016年 | 生理学・医学 | オートファジー(自食作用)の分子メカニズムを解明 |
| 本庶佑 | 2018年 | 生理学・医学 | 免疫制御分子PD-1の発見によるがん治療への応用 |
| 吉野彰 | 2019年 | 化学 | リチウムイオン電池の開発 |
| 坂口志文 | 2025年 | 生理学・医学 | 制御性T細胞(Tレグ)の発見による免疫制御機構の解明 |
| 北川進 | 2025年 | 化学 | 光を使って分子を精密に組み立てる超分子化学の実現 |
これらの研究はいずれも、従来の常識を覆し、新しい分野を切り開いたもので、まさに「世界の研究の方向を変えた」功績と言えます。
出典:ANNnewsCH