オートファジーは、細胞の中で古くなった成分を分解・再利用する「細胞のリサイクル機能」です。
近年、「16時間断食(時間制限型ファスティング)」を行うことで、このオートファジーが活性化すると言われています。
この記事では、なぜ16時間がひとつの目安とされるのか、その科学的根拠や注意点をやさしく解説します。
さらに、理解を深めるためのおすすめ書籍もご紹介します。
オートファジーとファスティングの関係
オートファジー(autophagy)とは、細胞の中で不要になったタンパク質や壊れた構造を分解し、再びエネルギーや素材として利用する仕組みです。
この働きは、栄養が不足した状態や軽いストレス状態で特に活性化しやすくなります。
ファスティング(断食)は、一定時間食事をとらないことで体内に「飢餓状態」を作り出し、オートファジーを促すと考えられています。
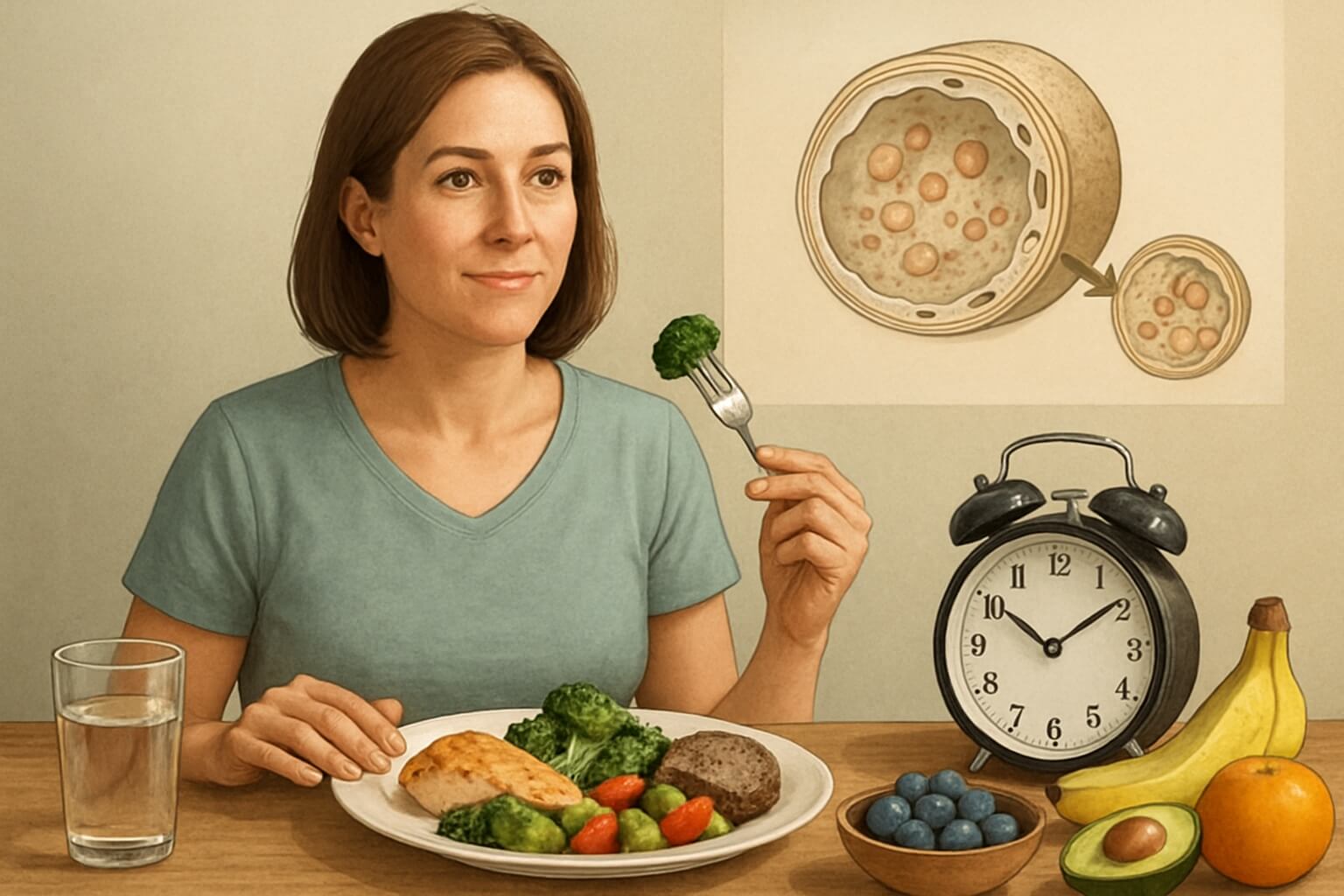
なぜ「16時間断食」で語られるのか
オートファジーが活性化するタイミング
一般的に、最後の食事から12~16時間ほど経過したあたりで、オートファジーが活発に働き始めると考えられています。
このため、16時間断食(16:8方式)が「断食時間を確保しやすく、効果を感じやすい方法」として広く知られるようになりました。
ただし、「16時間経てば必ず活性化する」といった厳密なデータがあるわけではなく、あくまで目安としての時間帯とされています。
エネルギー代謝の切り替え
断食を続けると、体はまず血糖を使い、次に脂肪を分解してエネルギー源とするようになります。
この時に作られる「ケトン体」という物質は、エネルギー代謝を変化させるだけでなく、細胞の修復やオートファジーの活性化を助けるとも言われています。
この代謝の切り替えが起こるのがおよそ12時間前後とされるため、16時間断食はそのサイクルを意識した方法といえます。
研究データと実際の効果
近年の研究では、時間制限型ファスティング(1日のうち16時間を断食時間にあてる方法)が体重減少や血糖値の安定に効果があるという報告があります。
ただし、オートファジー自体を直接測定した研究はまだ限られており、「16時間断食がオートファジーを何倍にも高める」といった表現は、現時点では科学的根拠が十分とは言えません。
そのため、「16時間」という数字はあくまで実践しやすい目安であり、個人の体質や生活リズムに応じて調整するのが現実的です。
注意すべきポイントと限界
オートファジーやファスティングは健康効果が期待できる一方で、過度な実践や誤った理解には注意が必要です。
- ヒトを対象とした長期的な研究はまだ少ない
- オートファジーは断食状態でのみ働くわけではなく、通常時にも一定のレベルで行われている
- 極端な断食は免疫低下やホルモンの乱れを引き起こすリスクがある
- 年齢・性別・体質によって効果が出やすい人と出にくい人がいる
無理に断食時間を延ばすよりも、自分のペースで続けられるリズムを見つけることが大切です。
出典:PIVOT 公式チャンネル