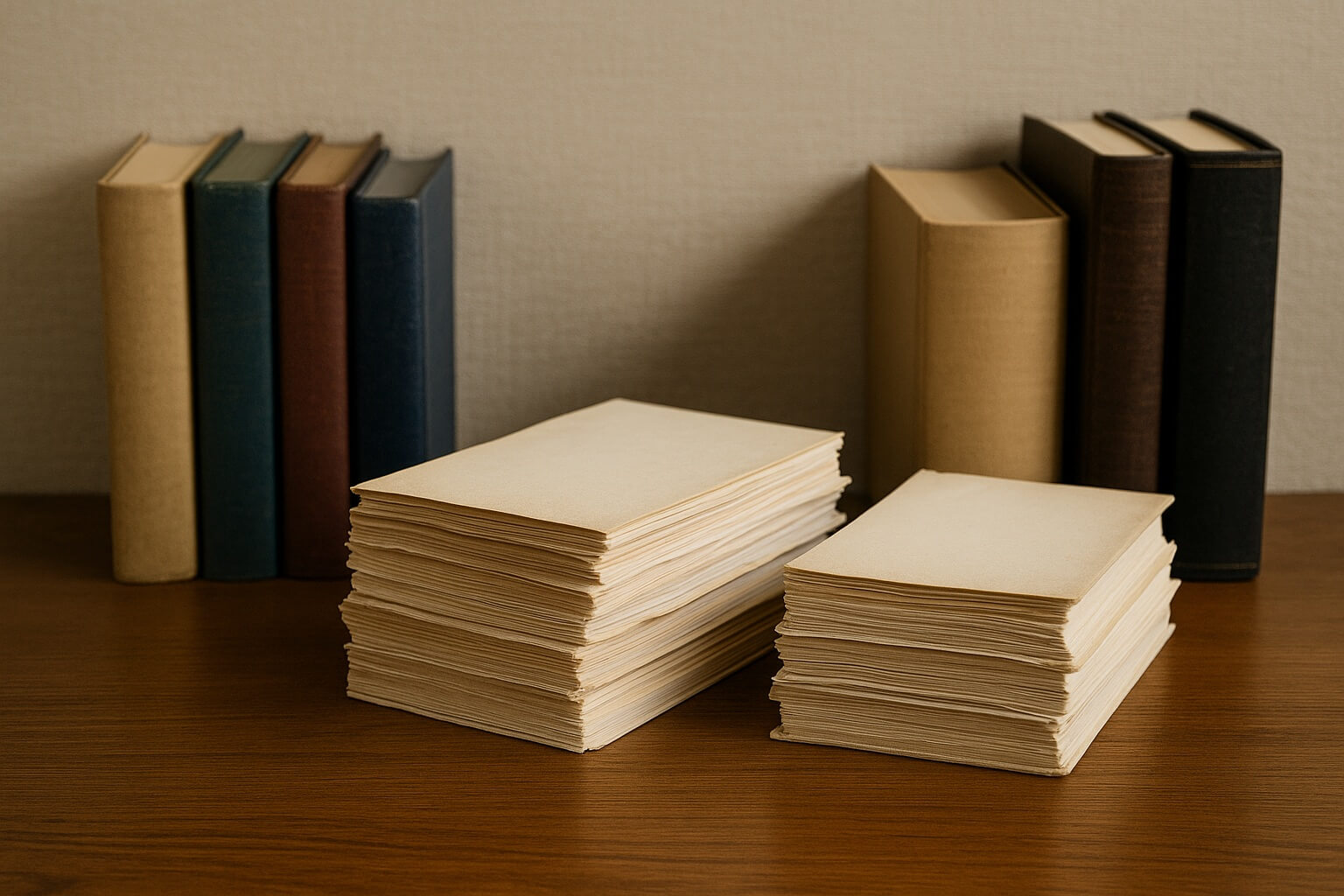3.他の文学賞との比較に見る芥川・直木賞の特異性
日本には芥川賞・直木賞以外にも多くの文学賞が存在する。たとえば、山本周五郎賞や本屋大賞、三島由紀夫賞、新潮新人賞など、それぞれの特色を持った賞がある。
その中でも芥川・直木賞が持つ最も大きな特徴は、「該当作なし」を厭わない厳格な姿勢にある。たとえば、アメリカのアカデミー賞では、原則としてすべての部門で受賞作が選出される。一方、芥川賞・直木賞は「無理に選ばない」ことを美徳としうる、極めて日本的な価値観が反映された制度でもある。
この“空位”を可能にする構造は、文学の本質を問うているという意味で非常にユニークだ。
また、本屋大賞のように書店員の投票で決まる賞では「読者の感動」が重視されるが、芥川賞・直木賞は「表現の純度」や「構成の深度」に重きを置く。
つまり、売れるかどうかではなく、「文学としての到達点」に評価の軸が置かれている点に、文学賞としての本質が見て取れる。
だからこそ、受賞作がないことが「妥協なき文学の証明」として、多くの読者や作家に強いメッセージを投げかけているのだ。
出典:ミステリー文学の本棚
まとめ
2025年上半期、芥川賞と直木賞の両方が「該当作なし」となったのは、文学の水準や選考の厳しさを改めて浮き彫りにする出来事だった。
形式としての選考基準は変わらないものの、審査の「運用」には柔軟性があり、今回は特に「表現と構成における文学性」が重視されたことが伺える。
この決定が文学界に与える影響は大きく、今後の受賞作に対する期待値も一段と高まるだろう。
一方で、「売れる小説」だけではない価値を問う、純粋な文学の視点を私たち読者も共有する必要があるのではないだろうか。
SNOWさんの思い出
僕は会社で新人のころに、芥川賞取りたいですねー、と半ば本気で同僚たちに語っていた族の者です。
文章が得意というより国語が得意で、文章というか作文がうまくなかったので、うまくなりたかったのですね。
特に動画でも出ていた京極夏彦さんや、村上龍さんの小説をよく読むというほどではないけど、たまに読んでいました。
それでだんだん文章を書くとは、より良い思想とはみたいな方向性になっていきました。
それで、有名な哲学の本とか、超勉強法で有名な野口悠紀雄先生の本を読んだりしていました。
もちろん超文章法も読んで、こういうのを書くのに活かされていた時期もあって、いまはほぼロジックを意識せずに書けるようになりました。
そういうのが色々わかって、芥川賞、もし応募したとして、取れたら奇跡だなぁと思うに至りました。
(何の話?)
今回の読書をもっと深める、おすすめの商品
芥川賞・直木賞をとる! あなたも作家になれる
そのままドストレートな内容の本ですが、これを読んだからと言ってとれるわけではないとは思います。
でも道しるべ的な本なので、もし目指そうという方がいらっしゃったら、迷子にはならずに済むかもしれません。